| この実践は日本文教出版株式会社の中学校 美術1年の教科書(18年度から)と指導書に採用されることになりました。 (2005年8月17日UP) |
||||||
教科書掲載について来年度の中学生が使用するのですが、私の手元にはもう教科書が届いているので、遠くから見た写真をアップします。作品には著作権がありますので、はっきり掲載できない点をご了承ください。  ←右下の緑っぽい作品です。 ←右下の緑っぽい作品です。中学校の先生方は、教師用指導書に実践例を掲載いたしましたので、18年度以降の指導書をご覧ください。執筆者の名前は載らないそうなので、実践内容で探してください。 |
||||||
題材設定の理由これは、自然物の美しい形や、身の回りのものの形を映像によって重ね合わせて、そこから、美しかったりおもしろい形になりそうな部分を選び、シンメトリー化をして色の調子を変えながら、生まれてきた新しい形の創造を楽しもうという題材です。作品を制作していく上で、発想力はとても重要です。そこで自然物や身の回りのものの形を組み合わせて、そこから新しい形を発見し、美しさを感じる作品作りをすることを通して、発想力を高めたいと考え実践しました。 また、コンピュータを使うことにより、ふだん絵を描くことが苦手だと感じている生徒でも制作を楽しむことができます。別の利点として、シンメトリー化をすることで、コンピュータならではの反復機能や反転機能の活用ができ、パターンを繰り返すことによって生まれる美しさも追究できます。 指導計画(1)学習内容を知る。(2)自然物や身の回りのものの形を探して、デジタルカメラ、スキャナーで取り込む。 (3)グラフィックソフトの扱い方を学ぶ。 (4)作品にしてみたい画像を自分のパソコンに取り込み、重ね合わせ方を工夫し制作していく。 (5)鑑賞会を開き、自分の制作を振り返るとともに、友達の作品の良さを鑑賞する。 参考作品(生徒作品は著作権の関係で掲載できません。)
たとえばこのような素材を重ねて |
 |
 |
 |
 ←フリー素材です。 ←フリー素材です。 |
配置をいろいろ考えて、
 |
ある部分を並べてシンメトリーにするとこうなります。
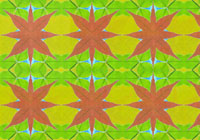 |
もともと、小中学生向けに作られたグラフィックソフトなので、2時間ほど使い方を学習すれば十分に使いこなすことができます。